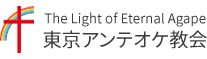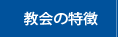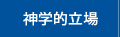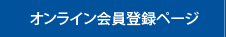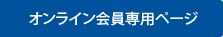日本の殉教者について
●=死者 ■=処刑方法
| 西暦 | ●=出来事 ▲=死者 ■=処刑方法 |
| 1549 | ● ザビエル伝道開始 |
| 1587 | ● 豊臣秀吉により天正禁令発布(キリスト教禁教令) |
| 1597 | ● 日本二十六聖人殉教 |
| ▲ 日本最初の殉教者 | |
| ■ 磔 | |
| 1602 | ● 長(山口県)における殉教 |
| ▲ 熊谷元直とその一族、11名。 | |
| ■ 斬首 | |
| 1603 | ● 加藤清正によるキリシタン迫害の始まり(熊本県) |
| ▲ 八代のキリシタンたち | |
| ■ 斬首 | |
| 1609 | ● キリシタン指導者とその子どもたちの殉教 |
| ▲ 肥後のキリシタン指導者2名とその子2名 | |
| ■ 斬首 | |
| 1612 | ● 有馬キリシタン指導者の殉教 |
| ▲ 指導者ミゲルとマチヤス | |
| ■ 斬首 | |
| 1613 | ● キリシタン武士の殉教 |
| ▲ 女、子どもを含む八名 | |
| ■ 火あぶり | |
| 1614 | ● 徳川幕府によるキリシタン禁令 |
| 検索の緻密さと厳重さ、拷問と処刑の残酷さ、そして二百数十年にわたるキリスト教迫害として世界でもまれな信仰弾圧である。 | |
| 1614 | ● 有馬における迫害と殉教(長崎県) |
| ▲ 44人の殉教者と凄惨な拷問(八角棒で足挟み) | |
| ■ 八角の太い棒に両足を挟み一方の端を縄でくくり、他の端を三人の兵が力一杯締めつけ、一人がその棒の上に乗って押しつける。 | |
| 1614 | ● 口之津の大殉教(長崎県) |
| ▲ 22人の殉教者と凄惨な拷問 | |
| ■ 両手両足を背中で縛り、木につるし重い石を背中に乗せ、責める。聞かないと地面におろし、手足の指を切り落としある人たちは、鼻をそがれた。また、指や膝の下を切り落とされ、石段下まで落とされた人たちもいた。 | |
| 1614 | ● 小浜での殉教。背教した者の密告による |
| ▲ 影響力の強かった4人の武士。 | |
| ■ 手足の指を切り落とされ、鼻をそがれた。その後冬の砂浜に放置され、殉教 | |
| 1617 | ● 大村で二十六聖人の殉教以後、最初の外国人宣教師の殉教 |
| ▲ 大村藩の藩主が背教し、その後迫害の嵐が吹く。4人の外国人宣教師 | |
| ■ 斬首 | |
| 1619 | ● 京都の大殉教 |
| ▲ 将軍秀忠の名により、捕縛された52名。(別に2才の男のからなる、8人の牢死者がいる。)この年、全国的に将軍秀忠の命により多くの殉教者たちが出た。 | |
| ■ 火刑 | |
| 1622 | ● 元和の大殉教 |
| ▲ 老幼男女55人の殉教 | |
| ■ 25人(神父、修道士、指導的信徒)は火刑、31人は斬首。(斬首されたのは、火刑となった男性の妻や子ども(4才)、すでに殉教によって夫を失った未亡人たちであった。) | |
| 1622 | ● 大村での迫害 |
| ▲ 6名の神父及び奉仕者 | |
| ■ 火あぶりと斬首 | |
| 1623 | ● 江戸の大殉教 |
| ▲ 将軍家光の命により江戸在住のキリシタン50人の殉教 | |
| ■ 火刑 | |
| 1624 | ● 大村での迫害 |
| ▲ 4名の神父と修道士 | |
| ■ 火あぶり(わざと縄が焼け逃げ出せるようにした。) | |
| 1627 | ● 雲仙地獄での殉教 |
| ▲ 長崎県雲仙市で26人の殉教(女、子どもを含む) | |
| ■ 雲仙の硫黄の湯に落とされる。皮膚はただれ、6時間かかって死んでいった者たちもいた。 | |
| 1629 | ● 東北各地での殉教 |
| ▲ 33名の殉教者 | |
| 1630 | ● 東北各地での殉教 |
| ▲ 89名の殉教者 | |
| 1632 | ● 長崎西坂での殉教 |
| ▲ 外国人宣教師、日本人神父を含む6名 | |
| 1633 | ● ジュリアノ中浦神父殉教 |
| ▲ 同神父をはじめ4名 | |
| ■ 処刑内容 穴づり | |
| 1633 | ● イエズス会士 |
| ▲ イエズス会士24名 | |
| 1634 | ● 長崎県大村での殉教 |
| ▲ 71名(男性46人/女性25人) | |
| 1634 | ● 長崎での殉教 |
| ▲ 500名以上の殉教者。次兵野衛神父の居場所を吐かせるため,拷問を行い殺害した。 | |
| ■ この後、次兵野衛神父の教えを受けた人々、延べ637人が殉教した。 | |
| 1635 | ● 蝦夷での殉教者 |
| ▲ 106名の殉教 | |
| 1636 | ● 細川藩での殉教 |
| ▲ 細川藩の重職を担っていた武士一家、15名 | |
| 1637 | ● 次兵野衛神父の殉教 |
| ▲ 中心的指導者であった次兵野衛神父と宿を提供したキリシタン12名の殉教 | |
| ■ 水責め、金剛杵で足と腕を突き刺し貫通させた。死にそうになると介護をし、何度も苦しめた。2度に渡る穴吊りで殉教 | |
| 1642 | ● 外国人宣教師の殉教 |
| ▲ 背教してしまった、フェレイラ神父を説得すべく来日した宣教師7名の殉教 | |
| ■ 水責めと穴吊りにより殉教。 | |
| 数々の崩れ(江戸時代、多くの一斉検挙(崩れ)が起きた。この検挙事件は懸賞金にほしさの密告のものが多かった。) | |
| 1644 | ● 濃尾崩れ(愛知) |
| ▲ 20数人の検挙 | |
| ■ ほとんどが牢死 | |
| 1657 | ● 大村藩(長崎県大村市)郡崩れ |
| ▲ 608人の検挙 | |
| ■ 411人が斬首、99人が放免、牢内病死78人、永牢2人 | |
| 1660〜1682 | ● 豊後崩れ(大分) |
| ▲ 220人の検挙 | |
| ■ 57人が死罪、牢死59人、放免65人、江戸送り3人 | |
| 1661〜1665 | ● 濃尾崩れ(愛知) |
| ▲ 200名余の殉教 | |
| 1668 | ● 濃尾崩れ(愛知) |
| ▲ 756名の殉教者と残労者405との記録がのこっている。 | |
| 1790 | ● 浦上一番崩れ |
| ▲ 19人の検挙者 | |
| 1839 | ● 浦上二番崩れ |
| ▲ 背教したキリシタンの密告により、4人の指導者の検挙 | |
| 1856 | ● 浦上三番崩れ |
| ▲ 背教したキリシタンの密告により、地下教会組織の多くの指導者が検挙され、組織が崩れてしまう。 | |
| 1867 | ● 浦上四番崩れ |
| ▲ 自葬問題を発端とし68人が検挙される。長崎県一帯の大迫害がここに始まる。 | |
| 1868 | ● 一村総流配 |
| ▲ 江戸幕府から明治政府に変わるも、1868年5月17日に大阪で御前会議を開いてこれを討議、「信徒の流罪」が決定した。 7月9日 、木戸孝允が長崎を訪れて処分を協議し、信徒の中心人物114名を津和野、萩、福山へ移送することを決定した。以降、1870年(明治3年)まで続々と長崎の信徒たちは捕縛されて流罪に処された。彼らは流刑先で数多くの拷問・私刑を加えられ続けたが、それは水責め、雪責め、氷責め、火責め、飢餓拷問、箱詰め、磔、親の前でその子供を拷問する、食事は腐った米、などその過酷さと陰惨さ・残虐さは旧幕時代以上であった。 |